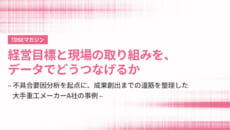目次
はじめに
「AI導入を掲げたが、現場が動いてくれない」
「PoC(実証実験)までは進んだが、本番運用に乗らず、立ち消えになった」
多くのDX推進担当者が、こうした“PoC疲れ”とも言える状況に直面しています。
高度なアルゴリズムや最新技術を用いているにもかかわらず、なぜデータ利活用プロジェクトは成果につながらないのでしょうか。
その要因は、技術そのものではなく、「経営目標と現場の業務、そしてデータをどうつなぐか」という設計にあると語る人物がいます。
データサイエンティストとして15年以上のキャリアを持ち、TDSEにて数多くのプロジェクトを現場定着へと導いてきた水野氏。
大学、大学院では情報デザインを専攻し、博士課程まで研究に取り組んできた経歴を持ち、現在はデータ利活用アセスメントサービスの責任者として、データ利活用を「企画・設計」の観点から支援しています。
「AIモデルを作る前に、まずお客様の業務を理解する。そのために、時には“新人用の教科書”から学び直すこともあります」
水野氏の言葉の背景には、PoCを単なる実験で終わらせず、次の意思決定につなげるための一貫した思想があります。
では、その思想は、現場でのどのような経験や課題認識から生まれたのでしょうか。
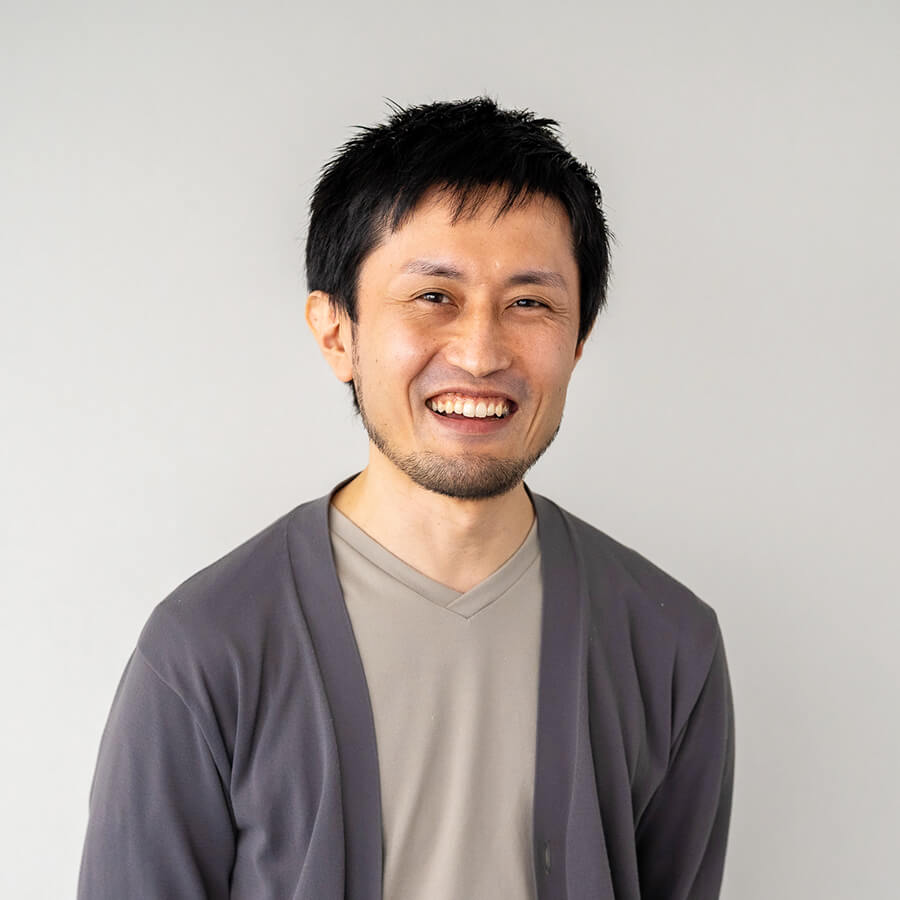
サービス責任者プロフィール
水野 亮
TDSE株式会社
コンサルティング本部 グループ長
大学及び大学院にてシステム情報科学を専攻。
2010年にアナリティクスコンサルティング会社に入社。2014年からTDSEにて鉄鋼メーカー、電子機器メーカー、電子部品メーカー、保険会社、消費者金融、人材メディア等、多種多様な分野のデータサイエンスプロジェクトに従事。特に製造業顧客のDX推進支援をリードし、ウェビナー登壇も多数。
なぜ、多くのデータ利活用は「PoC」で止まってしまうのか? ~現場協力が得られない構造的要因~
まずは、多くの企業で共通して見られるつまずきの構造から整理してみましょう。
データサイエンスという言葉が出てきた頃は、データ利活用やAI活用に取り組む企業は一部に限られていました。しかし近年は多くの企業で導入が進み、今や1社につき複数のデータ/AI利活用プロジェクトが走っているのが当たり前の時代となっています。
しかし、業務プロセスに定着し「成果が出ているプロジェクト」は一部であり、まだまだ打率が低いのが実情です。これからは「数打てば当たる」では通用せず、プロジェクト成功の打率を上げていかなければ、企業の競争力を維持できないフェーズに来ています。
なぜ、多くのプロジェクトはレポート報告だけで終了してしまうのか。
水野氏はその主要な要因として、技術的な課題以前に「現場の協力が得られないこと」を挙げます。
「現場の方々は、日々の失敗が許されないミッションクリティカルな業務で手一杯です。そこに『AIのためにデータを出してほしい』『業務フローを変えてほしい』と言われても、現場にとっては負担が増えるだけです。『プロジェクトが成功しても、自分たちの評価や給与に直結するわけではない』というのが、偽らざる本音ではないでしょうか」
現場にとってメリットが見えず、かつ自分たちの言葉(業務用語・専門用語)が通じない“外部”の取り組みは、警戒や抵抗を生みます。
その結果、必要なデータが集まらず、テスト運用も進まず、プロジェクトはPoCの段階で停滞してしまうのです。
「PoCは、本来“やるか・やらないか”を判断するための重要な検証です。問題なのは、 PoCがいつの間にか『技術検証』や『機械学習の精度検証』だけにすり替わってしまうことです。本来意思決定に必要な『ビジネス効果の目標達成』や『現場の負担も含めた実現可能性』の検証にコミットできていないことが、次のステップに進めない最大の要因です」
と水野氏は語ります。
PoCを通じて何が分かり、次にどの選択肢を取るのか。
この意思決定まで設計されていない場合、PoCは現場にとって“やらされ仕事”となり、DX推進組織そのものへの信頼を損なう原因になってしまいます。
では、PoCを「次の意思決定」につなげるためには、何が必要なのでしょうか。
その答えが、水野氏の言う「科学(サイエンス)」のアプローチです。
TDSE流「科学(サイエンス)」のアプローチ ~暗黙知を意思決定可能なロジックへ~
TDSEが重視するのは、単なるAI開発や自動化ではありません。
水野氏は、自らの役割を次のように表現します。
「たとえば製造業で語られる技能継承の問題ひとつを取っても、現場には何十年にもわたって培われてきた技術や勘所があり、現場も経営も、そこに強い誇りを持っているはずです。にもかかわらず、「AIで簡単に自動化できます」と語るケースを目にすることがあります。
しかし私は、それは違うと考えています。
私たちの仕事は、長年積み重ねられてきた技能や判断の背景を、表面的に置き換えることではありません。まず徹底的に業務を理解し、データを分析し、データだけでは見えない部分は現場へのヒアリングを通じて掘り下げ、なぜその判断が行われてきたのかをロジックとして明らかにしていく。
そうして初めて、技能や勘所を科学的に再現可能な形へと一般化し、モデルとして表現することができます。私は、この一連のプロセスこそがデータサイエンスだと思っています。
このプロセスを飛ばしてしまえば、お客様のビジネス課題を本当に解決することも、データ利活用で継続的な成果を出すこともできません。
技能や勘所は、置き換えるものではなく、理解し直すものです。そこに向き合わずに作られたAIは、現場にも、経営にも、決して根づきません。」
現場の技能や職人芸は、汎用的なAIツールを導入するだけでは再現できません。
重要なのは、その判断や作業が、
・どのような物理現象・業務条件に基づいているのか
・数値としてどう表現できるか
を一つひとつ解き明かし、「なぜその判断が行われてきたのか」を意思決定可能なロジックとして整理することです。
こうして現場の暗黙知を科学的に捉え直すことで、初めてデータは、現場だけでなく経営との対話にも使えるものになります。
これが、TDSEの考えるデータを使った科学(サイエンス)です。
たとえば、「生産コストを30%削減したい」という経営課題があった場合、TDSEでは、「AIなんだから90%は必要だ!」などの根拠のないAI精度に置き換えることはありません。
まず、どの業務が生産コストに影響しているのかを整理し、「生産コスト30%削減のためには、該当業務の歩留まりをどの程度改善する必要があるのか」を分解します。
その上で初めて、AIの予測精度として80%で十分なのか、あるいは95%が必要なのかなど根拠に基づき、且つ定量的に検証可能な試算ロジックを策定していきます。
このように、ビジネスの言葉と技術の言葉をつなぎ直し、関係者が同じゴールを共有できる状態を作ることを重視しています。
専門書による「共通言語」の習得 ~現場の信頼を変えた小さな行動~
TDSEが重視する、ビジネスと技術をつなぐ「翻訳」の考え方が、実際にプロジェクトの停滞を打破した事例をご紹介します。
ある電子部品メーカー様におけるプロジェクトでの出来事です。
テーマは「コンデンサの検査工程の最適化」でした。
経営としては、工場のスマートファクトリー化を進め、数十%規模のコスト削減を実現したいという目標がありました。その一環として、複数回にわたって実施されている検査工程を見直し、膨大な検査工数を削減したいという要望がありました。
一方で、この検査工程は品質に直結する極めて重要なプロセスです。現場からは、「AIによる自動判定」に対する強い懸念が示されていました。さらに、会議では「抵抗値」「静電容量」といった専門用語が頻出し、当初は意思疎通そのものが難しい状況だったといいます。
この状況を前に、水野氏率いるTDSEチームは、いきなり解決策を提示することはしませんでした。
「まず、対象を理解しなければ真に課題解決のための検査システムは構築できません。安易な自動化では必ず後々問題が発生します。よくある失敗の一つは、精度検証設計の誤りです。現象を理解せずに世の中にある一般的な機械学習の精度検証指標などを用いてしまうと、意味のない検証設計になりがちなのです。その検証設計に基づいていくら精度が高くなったとしても、検証方法自体が誤りなのですから、実際に運用すると問題が発生するわけです。また、根本的には同じ意味ですが、なぜ検査を自動化して大丈夫なのかを共通言語で説明することができなければ、現場や経営層含めステークホルダが納得し安心して利用して頂くこともできません。そこで私たちは、そのメーカー様の新入社員が学ぶ『コンデンサの基礎知識』に関する専門書を購入し、チーム全員で読み込みを行いました」
次の会議では、TDSEのメンバーが現場と同じ専門用語を用い、適切な文脈で議論を進めました。そのとき、現場の反応が明らかに変わったといいます。「このチームは、自分たちの業務を本気で理解しようとしている」そう認識された瞬間でした。
信頼関係を構築した上で、検査回数を一律に減らすのではなく、製品や条件ごとに「適切な検査回数」を判断できるよう、現場と共に整理を進めました。
この工場では、製品の品質を担保するため、同一製品に対して複数回の検査が行われていましたが、過去の検査データや不良履歴を分析すると、製品の種類や製造条件によって、不良が発生しやすいケースと、極めて発生しにくいケースが明確に分かれることが分かってきました。
そこでTDSEは、「この条件に該当する製品は従来通り2回検査を行う」、「一方で、これらの条件を満たす製品については、検査を1回にしても不良品流出のリスクは極めて低い」といった形で、検査回数を一律に減らすのではなく、条件付きで判断できるロジックを整理しました。
このように、“減らしてもよい理由”をデータとロジックで可視化したことで、現場は「なぜこの製品は1回でよいのか」、「なぜこの条件では従来通り2回必要なのか」を納得した上で判断できるようになりました。
その結果、品質への不安を残すことなく、検査回数の見直しについて現場と合意形成が進み、検査工数の削減が現実的な選択肢として浮かび上がりました。
これは単なる現場改善にとどまりません。検査工数の削減は、経営が掲げていたコスト削減という目標に直結する成果でもあります。
こうして整理された判断ロジックと運用方針による効果は、実は当初見込んでいた工数削減効果よりも小さいものでした。しかし、リスク低くかつ改善が見込める現実的なラインとして根拠を持って改めて見込みなおした効果は、現場も経営層も納得のいく数値であり、現場接続のハードルを越えるに十分な材料となりました。
まとめ:アセスメントが果たす役割― 単発で終わらせないための設計図 ―
データ利活用プロジェクトにおいて、PoCの繰り返しや予算超過以上に回避すべきリスクがあります。 それは、「現場からの信頼喪失」です。
こうした事態を避けるために重要になるのが、現場の業務課題、経営目標、そしてデータを丁寧につなぎ、現場で実装されるデータ利活用の形をあらかじめ描くことです。
TDSEのデータ利活用アセスメントサービスでは、この整理と設計のノウハウを基にソリューションのアセスメントを行います。
水野氏は次のように語ります。
「アセスメントは、テーマに点数を付けて終わるものではありません。それぞれの取り組みがどう関係し合い、どの順番で進めることで相乗効果が生まれるのか。そこまで含めて“企画”としてデザインすることが重要です」
実際、過去のプロジェクトでは、単体のAI導入ではなく、3年間のロードマップを策定し、段階的にテーマを展開する提案が採用されたケースもあります。
どのテーマから着手し、どの検証結果をもって次に進むのか。
アセスメントは、その判断軸を言語化し、組織として共有するためのプロセスでもあります。
水野氏は、データ利活用に取り組む企業の皆様へ、次のように呼びかけます。
「困難な課題であっても、まずは『どのような状態が理想か』を議論し、未来の企画を共に作り上げましょう。私たちTDSEが、その実現に向けて現状のデータの量と質や現場の状況で現実的にできるところから、理想に向かって着実に登っていくロードマップを策定し、次の一手を選べる状態をつくることを支援します」

TDSEは、技術導入ありきではなく、検証と整理を重ねながら、次の意思決定につながるデータ利活用を支援します。
まずはアセスメントというスモールスタートから、確実な一歩を踏み出してみませんか。