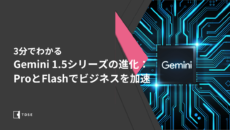Dify×TDSEトークセッションの開催
6月24日(月)、最近LLM界隈で話題となっているオープンソースのLLMアプリ開発プラットフォーム「Dify」を提供するLangGenius社のJason Wang様にご来社いただきました!
弊社内にもDifyに強く関心を持ったデータサイエンティスト、エンジニアが多くおり、社内向けのトークセッションを開催させていただきましたので、本記事ではその様子をレポート致します!

DifyがTDSEに来る!?と小耳にはさんだのが約2週間前。
「直接話を聞いてみたい!」という社員が多くおり、Jasonさんに社内向けのサービス紹介とQAの時間を設けたいとお願いしたところご快諾頂き、今回のトークセッションを実施することとなりました。
普段テレワークで働く社員が多い中、この日ばかりはこのトークセッションを楽しみに出社した社員でいつもよりにぎわう社内。期待が高まります。
Difyのご紹介
まず、JasonさんからDifyとは何か、Difyによってどんなことが実現できるのか、についてご紹介いただきました。

Difyとは
ITやLLMの専門知識が無い人でも操作できる直感的なUIが強みである
Difyの活用例
活用例として4つのユースケースをご紹介いただきました。
カスタマーサポート
マーケティング
研究開発
内部アシスタント
QA
QAでは、実際の業務活用に関する質問が飛び交いました。
質問の一部をご紹介します。
Q. オンプレミスとクラウドベース、どちらで提供することが多いか?
A. どちらの形態でも使っていただいているが、エンタープライズや日本企業はセキュリティなどを考慮したうえでオンプレミスを選ぶ場合が多い。
Q. Difyを使用している場合、LLMのバージョンアップの際にユーザー側としてはどのような対応が必要か
A. バージョンアップの際もDifyのプラットフォームと簡単に統合出来る。GPT4がリリースされた際は4時間でDifyが新バージョンと統合するためのテンプレートを公開し、顧客はそれを使用することで自社のアプリをGPT4に対応させることができ、新バージョンで新たに追加された機能も活用可能となった
限られた時間でしたが、Difyへの理解を深めることができ、Difyのプラットフォーム上でLLMとワークフローのロジックを組み合わせることにより、ビジネスシーンでのLLM活用がより加速するイメージが掻き立てられる、貴重な機会となりました。
Jasonさん、ありがとうございました!

先端の技術やサービスを取り入れながら、ベンダーに依存せず中立的な立場でお客様の課題、環境、要望に合わせたご提案ができることがTDSEの強みの一つでもあります。 LLM活用支援サービスでは、アセスメントから構築、運用サポートまで包括的にご支援させていただきます。ご興味がございましたら、是非お問い合わせ下さい!