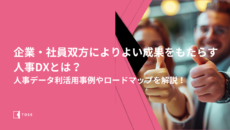近年は企業のDX(デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革すること)を支援する研修が増えています。
近年は企業のDX(デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革すること)を支援する研修が増えています。
しかし、実は研修で得られるスキルには限界があります。従業員に研修を受講してもらうだけで、DXを推進できる人材に育つとは限りません。
今回は「研修を受けただけの人」と「活躍できる人材」の間にあるギャップや、DX人材の育成方法について説明します。
目次
DX研修を受ければ「すぐに活躍できる人材」になるとは限らない

DX研修を受講した方のなかには、「研修を受ければすぐにスキルや考え方が身につき、DXを推進できる人材になれる」と考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、実際はそうとは限りません。
そもそもDX研修とは、企業のビジネスモデルを変革するための「デジタル技術」や「考え方」を学ぶ研修のことです。
研修で教わる「データ分析」や「プログラミング」といったデジタル技術は、あくまでDXを推進するための手段に過ぎません。
「何をするものか」が理解できても、「経営改革やビジネス改善のやり方」が身についていなければ意味がないのです。
では、ビジネスに貢献できる人材になるにはどのような点を補えばよいのか、詳しく見ていきましょう。
「研修を受けた人」と「活躍できる人」の間にあるギャップとは?

「研修を受けただけの人」と「実際に活躍できる人」の間にある一般的なギャップを、下記の表にまとめました。
各スキルを身につけられている場合は「○」、身につけられていない場合は「×」で表しています。
| 必要なスキル | 例 | 研修を受けた人 | 活躍できる人 |
|---|---|---|---|
| 基礎知識・技術 | ・データサイエンス ・AI ・プログラミング ・データベース ・データ加工 ・可視化集計 |
〇 | 〇 |
| ビジネスへの応用力 | ・事業理解 ・現状把握、整理 ・分析設計 ・考察 ・施策立案 ・実行 |
△ | 〇 |
| 必要なマインド | ・主体性(自ら動いて提案する力) ・好奇心(トレンド技術のキャッチアップ) ・仮説力(学んだ技術をどう業務に活かすか、仮説を立てる力) |
× | 〇 |
| DX推進・実行におけるコミュニケーション | ・課題整理、目的設定のためのヒアリング力 ・社内調整力 ・マネジメント力 ・柔軟性 |
× | 〇 |
上記のとおり、データサイエンスやプログラミングなどの基礎知識は、研修を受けたすべての人が身につけられます。
しかし、ビジネス上の課題を解決するためには、DXを推進する従業員自身に一定の「マインド」や「コミュニケーション」スキルがあることが欠かせません。下記がその一例です。
・「自社のどの業務にAI技術等を活かせそうか」など、仮説を立てようとする力
・他部門を巻き込みながら、現状の問題点を洗い出す力
また、プロジェクトを発足した後は小さくDXを進めていき、計画どおりにいかなかったときは方向転換できる柔軟性も必要です。
IT技術の進歩は早いため、DXを計画してから社内に導入するまでに何年もかかってしまうと、時代に取り残される恐れがあります。
以上のようなギャップを埋めていくことで、研修の知識をビジネスに応用し、DXを推進できる人材に近づくことが可能です。続いて、ギャップを埋めるためのポイントを見ていきましょう。
「活躍できるDX人材」へ育成する3つのポイント

従業員を活躍できるDX人材に育成する際は、下記3つのポイントを押さえておきましょう。
- DXを推進する人材を選ぶ
- 評価制度を明確にする
- 「ビジネスの実践」までが学べる研修を選ぶ
順番に説明します。
ポイント1.DXを推進する人材を選ぶ
まずは、DXを推進する人材を選びましょう。
たしかにDX研修を受講すれば、ある程度の基礎知識は身につけられます。しかし、マインドやコミュニケーション力は、従業員本人の素養によるところが大きいです。
研修だけで習得するのは限界があるため、あらかじめ「下記のスキルをもっているかどうか」を選定基準にしましょう。
| スキル | 詳細 |
|---|---|
| マインド | ・主体性(自ら動いて提案する力) ・好奇心(トレンド技術のキャッチアップ) ・仮説力(学んだ技術をどう業務に活かすか、仮説を立てる力) |
| コミュニケーション力 | ・課題整理、目的設定のためのヒアリング力 ・社内調整力 ・マネジメント力 ・柔軟性(計画どおりにいかない場合に方向転換できる力) |
もし社内に適した人材がいない場合、外部人材の採用も視野にいれる必要があります。
ポイント2.評価制度とインセンティブを明確にする
次に、DX人材に対する評価制度とインセンティブを明確にしましょう。
「スキルを『身に着けた』と言える基準」や「身に着けた際のメリット」を明らかにしておくことで、従業員の現在の業務に対するモチベーションがアップし、DXを推進できる人材になる可能性が高まります。
評価制度やインセンティブの例は、下記のとおりです。
| 制度 | 例 |
|---|---|
| DX認定制度 | スキルの習熟度に応じて「ブロンズ・シルバー・ゴールド」のランクを付与する ・ブロンズランク:上位者の指示に基づいて推進できる人材 ・シルバーランク:上位者の確認をもとに独力で推進できる人材 ・ゴールドランク:高度なDX技術を用い、組織全体の課題解決に向けて取り組める人材 |
| 表彰制度 | 1.個人またはチームでDX技術を活用し、業務改善・サービス向上・働き方改革などに 通じる取り組みから優秀なものを紹介する 2.DX推進に果敢に取り組んだメンバーを顕彰する |
努力や成果をしっかりと認める環境を作ることで、DX推進プロジェクトの一人ひとりが「自分ごと」として取り組みやすくなります。
経営陣が率先して評価制度を構築していきましょう。
ポイント3.「ビジネスの実践」までが学べる研修を選ぶ
DX研修を選ぶ際は、「身につけたスキルをビジネスで実践する方法」まで学べるサービスを選定する必要があります。
昨今はさまざまな企業がDX研修を実施していますが、ビジネスへの応用力まで身につけられる研修は多くありません。
そこでおすすめなのが、「DXコンサルティング会社」が提供する人材育成プログラムです。DXを実際に実行・支援しているので、学んだ知識をどう実業務に活かせばよいかを「事例に基づいて」教えられるからです。
弊社TDSEでは、DX人材を育成するサービスを提供しています。人材育成プログラムをとおして「ビジネスへの応用力」を身につけてもらうことに力をいれており、次のようなスキルの習得が可能です。
・分析設計:ビジネスの目的に応じて、適切な分析方法を設計する
・考察:分析した結果をもとに、ビジネスに活かすための仮説を導き出す
上記のようなスキルを身につける過程で、ヒアリング力や仮説力も養われます。結果的に、「研修を受けただけの人材」から「活躍できる人材」になるためのギャップを埋めることにつながります。
詳しいサービス内容は下記の資料で紹介していますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご覧ください。
「DX人材育成サービス」の紹介資料をダウンロードする
※無料でダウンロードいただけます
【参考】キャリアビジョンを描いてもらう
DX人材として活躍してほしい従業員には、キャリアビジョンを描いてもらうことが重要です。
弊社の経験上、DX人材として成功している人は、自身のキャリアアップをよく考えている人が多い傾向にあります。DXを学ぶことで「自分の人生がどのように好転していくのか」を明確にイメージでき、モチベーションも維持しやすいからです。
例えば「DXプロジェクトAが成功したら、別部署の新規DXプロジェクトBに着手する」という人もいます。さまざまなプロジェクトで成功体験を積み重ね、スキルアップを目指すなどです。
企業のDXを成功させるためにも、「従業員がキャリアをイメージしやすい体制づくり」を目指しましょう。
適切な人材や研修を選ぶことが、DXを成功させる秘訣

DXの取り組みを社内に浸透させ、推進していくためには、適切な人材を選定することが欠かせません。
今回紹介したマインドやコミュニケーション力をもった従業員を選定し、どのようなキャリアを構築できるのかしっかり説明しましょう。
その上で、ビジネスに応用できるスキルが身につく研修を選ぶことが重要です。